
| トロンボーン協奏曲的 「悲愴」 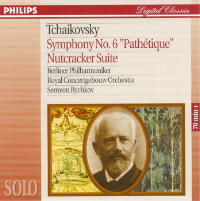 指揮:セミヨン・ビシュコフ 演奏:アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団 |
トロンボーン吹きにとって見せ場の多いこの曲はまた,古くはフルトヴェングラー近年はカラヤン,バーンスタインなど名演の多いことでも知られています。 また,題名付きの曲を好む日本人の性格からも,演奏会で取り上げられる機会の多い曲です。それだけに古今東西の指揮者が取り上げ必ずと言っていいほど録音する曲でもあり,超名演から聞くに耐えない愚演,あきれる迷演が存在していますし,これからも生まれ得る曲と言えます。 さて,ここで取り上げる演奏は,一時期名前が売れ,次代の大指揮者として期待されていたセミヨン・ビシュコフの指揮するアムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団(現:ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団)の演奏です。 録音時期はちょうど売り出し中の若手との宣伝文句の似合う1987年。私は特にビシュコフのファンではなかったので,買ってはいませんでした。 あるトロンボーンの先輩の家に遊びに行ったとき,「おもしろい演奏があるんだ。」と言ってかけてくれたのがこのCDでした。 3楽章が始まって普段聞こえないはずの部分でトロンボーンの音が聴こえ始め,最後の方はもう完全に全体のバランスを無視したトロンボーン協奏曲状態になってしまっていました。特にバス・トロンボーンの吹きすぎは凄いものがあり,聴き終わっての感想は「よくもまあ,指揮者,レコード会社はこんな録音の発売を許可したなー。」でした。 最近ようやくフィリップスのSOLO,DUOシリーズの一環として再発売されたので購入しました。残念なことにこのシリーズは録音をソフトな感じにリマスターする傾向があるようで,最初に耳にしたときのあの驚きは消し去られていたのです。 購入するなら是非,中古店で発売時の物か,もしくは廉価発売の物を購入して欲しいものです。みなさんも一緒にあきれようではありませんか・・・。 |
|
情熱的「オルガン付き」 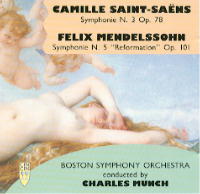 指揮:シャルル・ミュンシュ 演奏:ボストン交響楽団 CINCIN CCCD 1014  ちなみにこれがリビングステレオシリーズで出ている正規版。 ちなみにこれがリビングステレオシリーズで出ている正規版。 |
ミュンシュは熱い演奏をするので私の好みの指揮者です。パリ管時代には「幻想」の名演があり,ボストン響時代には「オルガン付き」ののスタンダードといえる名演があります。これはRCAの「リビング・ステレオ」シリーズの第1回発売の目玉として発売されたのでお聴きになった方も多いことでしょう。 最近放送録音を中心にしたライブ演奏のCD化が流行っています。最近の録音に個性が無く音楽の流れが感じられないのも一つの原因でしょう。店頭には最初は海賊版に近いようなMELODRAM,NUOVA ERA,HUNTなどが並んでいましたが,後にTHARAや,BBC Cassicsなどをはじめとする様々なレーベルが放送局や遺族の許可を得て発売するようになってきました。 録音も契約で行う関係からなかなか発売できない音源もあるようで,そんなとき比較的録音の良い海賊版が出るとつい買ってしまうと言うコレクターの性から私のCDライブラリーにもある程度の海賊版があります。 そんな中で,多分海賊版であろうと思われるレーベルCINCIN(フランス語で「乾杯」と言う意味)から,1962年4月20日にボストンシンフォニーホールで行われた演奏会の録音が出ています(1999年1月現在このCDは店頭にはありません(多分))。 正規版の録音は1959年4月5,6日なのでちょうど同じ場所で3年後の録音といえます。しかし,ミュンシュらしさが出つつも上品な正規版の演奏と比べこちらは全曲にわたってミュンシュ臭がプンプンです。録音時間がほんの数秒しか変わっていないにも関わらずです。特に音楽が激しさを増す1楽章前半部分の6分代からミュンシュの気合いの入った叫びが入り,その瞬間からオーケストラに火がつくのが解って楽しめます。また2楽章前半部分の始め,そして2楽章後半部分の盛り上がる部分からラストは圧巻です。大見得を切ってオーケストラを指揮するミュンシュが目に浮かびます。 最終部分に至っては,演奏がこれ以上ないくらいに熱くなり,同時に客席も興奮の度合いが高まっていきます。最後の音を延ばしたいだけ延ばしてしまったためにトランペット奏者の息が続かなくなって吹き直しをしているほか,その音が鳴りおわらないうちにブラボーのかけ声と万雷の拍手が巻き起こります。 トランペットの音がこの時代のアメオケに共通する安っぽさを出す事が気にならない人ならば是非聴いていただきたい『情熱的「オルガン付き」』です。 |
|
破滅的「革命」 指揮:アルトゥーロ・ロジンスキー 演奏:フィルハーモニック・シンフォニーオーケストラ・オブ・ロンドン(ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団) MCA dobule decker MCAD2-9823B 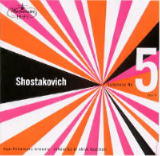 ウエストミンスター・レーベルの復刻によってオーケストラがロイヤル・フィルであることが判りましたので,文章も少し訂正させていただきました。 (2000年10月9日) WESTMINSTER原盤 MCAビクター MVCW-18008 |
あるレーベルを興すときたいていの経営者は比較的コストの安い室内楽から始め,そのうちにオーケストラのレパートリーに手を拡げるというやり方が一般的で,これは今も昔も代わりがありません。しかし,録音すること事自体が少なかった1960年代は,大指揮者と一部の名門オーケストラしか録音に耐えうるレベルには達していませんでした。 そんなときにウィーン・フィルのメンバーやウィーンの演奏家を起用して室内楽分野で名盤を数多く発売し今まさにオーケストラ作品に手を拡げようとしているウエスト・ミンスターと言うレーベルがありました。 この当時ウィーン・フィルはイギリスのデッカ(DECCA)と専属契約を結んでおり,大指揮者のほとんどもどこかに取られている状態でした。そのためオーケストラはフリーの腕利きのそろう場所。指揮者は専属契約はしていないが確実にオーケストラをある程度のレベルに引き上げる実力のある人物が必要でした。 そこでオーケストラはEMIが録音のために作り上げたフィルハーモニア管弦楽団に対抗してフィルハーモニック・シンフォニーオーケストラ・オブ・ロンドン(実は契約の関係で実体はロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団;),指揮者は厳格なリハでオケのレベルを向上させる実力を持ちながら,アメリカのオーケストラでは経営陣との対立からうまくいかずヨ−ロッパにもどっていた実力者のアルトゥール・ロジンスキーに白羽の矢が立ったのです。 そこに生まれた演奏は・・・,これはもしかしてレコードに納めるためではと思われるほどに馬鹿っ速い「革命」でありました。ロジンスキーは本当にこんな演奏で自分の芸術を表現できたと思っていたのでしょうか。自伝でも読めればその謎(と言うほどでもないでしょうが)が解けるでしょうが,とにかく1楽章からムラビンスキーなどを聴いていてはびっくりしてしまう速さです。そしてその速さは笑いを誘います。4楽章などはこの調子で始まったら中間の一番速い部分はどんな速度だろうかと心配してしまう速さです。 ただ,一瞬一瞬に,他の指揮者では見えなかったこの曲の別の側面を見せてくれることも確かです。本当の芸術家としての姿を記録しておいて欲しかったというのが本音です。 追伸: 最近オリジナルマスターテープによる再発売がなされ,素晴らしい音に甦ると共に音楽の説得力も増し,迷盤ではなく名盤に感じられるようになってきました。 |
|
唄うコントラバス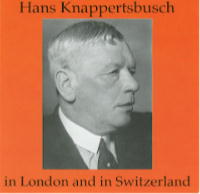 指揮:ハンス・クナッパーツブッシュ 演奏:スイスロマンド管弦楽団 PRISER RECORDS MONO 90189 この録音の原盤は英DECCA SAR234-1〜SAR243-1 |
みなさんは古い録音をどのように鑑賞しているのでしょうか? そのまま最新録音と同じように聴いているのでしょうか? 野村あらえびすではありませんが,「良い曲,良い演奏,良い録音」がクラシック鑑賞の基本であることは今も昔も変わり有りません。ですが,良い録音でなくても良い演奏は沢山あることもご存知のとおりです。特に最近の録音に共通する「指揮者の顔が見えない(個性のない)」演奏ではいくら録音に最新のテクノロジーを駆使したところでつまらないことこの上ありません。良い演奏かは兎も角,最近流行の放送音源や未CD化のSP群の復刻はそんな演奏に飽きた人々の渇望を癒すものです。残念ながらこちらには最新テクノロジーの録音を聴いてしまっている耳には「良い録音」とは言い難いのが現状です。 私も「きっと良い演奏なのだろうけど」,「ここが聴かせるのだけれど」と思いつつ聴き通していられないことがありました。特に時間的,精神的余裕が必要なはずの鑑賞が出来ないために,入っている録音に期待して買ったはずのCDが聴かずに山積みになって久しくなっていました。 ところがある日,住宅や時間的事情から,今までそのステレオ感の不自然さが嫌で敬遠してきたヘッドホンでの鑑賞を,「モノラル録音だからいいか」と言う軽い気持ちで行ったところ,以外にもこれが古い録音の鑑賞に有効なことに気が付いたのです。スピーカーから近所に気兼ねしながら小音量で鑑賞していたときには気が付かなかった演奏の精気が立ち現れたのです。この方法で再認識した演奏家,録音は数多く,みなさんにも是非試していただきたいと思います(なにを今更・・・。) さて前置きが長くなりました。本題です。 クナッパーツブッシュ(以下「クナ」)というドイツの指揮者がいます。ワーグナーの楽劇や,ブルックナー,ブラームス等に不朽の名盤と言われるものを残し,また練習嫌いから様々な逸話を残した『巨匠』です。 デッカが録音したSPの復刻が出たので買ってみました。前述の方法で鑑賞したところSPにありがちな盤面ごとの録音からくる演奏の不連続性(盤面ごとの録音をするからです。)を越えて共通するクナの素晴らしさが私を虜にしました。昔から低音部が好きだった私にとっても初めて聞くブラ2だったと言えるでしょう。クナは低音部を特に大事にしていました。そして唄わせたのです。 コントラバスパートがこんなにも詩に溢れていたとは!!思わずスコアで確認してしまったほどです。新しくそして感動的なこの演奏に久しぶりに聴き惚れ,時間を忘れて最後まで聴き通してしまったのです。 皆さんにも是非この鑑賞法でこのCDをコントラバスパートに注目しながら聴いてもらいたいと思います。きっと新たな発見があることでしょう。 |
|
録音の魔術!! 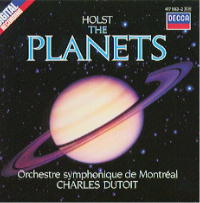 指揮:シャルル・デュトワ 演奏:モントリオール交響楽団 DECCA 417 553-2 サン・サーンス:「オルガン付き」  指揮:シャルル・デュトワ 演奏モントリオール交響楽団 DECCA 410 201-2 エルガー:エニグマ変奏曲  指揮:シャルル・デュトワ 演奏:モントリオール交響楽団 DECCA 430 241-2 |
SP,LP,CDといった録音を聴く楽しみは,時を越え,場所を選ばず,好きなときに好きな部分を聴ける所にあり,もう一つ,録音の良さを味わうオーディオ・マニア的楽しみにあるといえるでしょう。 録音技師たちは偉大な演奏家の芸術をより良い音で残そうと努力を重ねました。 ステレオ録音の時代になると様々なレーベルが様々な録音方法で,自分のレーベルの録音方式こそがアーティストの意志を代弁し,オーディオマニアを満足させる素晴らしい録音であることを喧伝しました。50〜70年代がそのような録音方式が乱立した戦国時代でした。 録音方式にはRCAのリビング・ステレオ,デッカのffss(フル・フリークエンシー・ステレオフォニック・サウンド),フェイズ4,EMIのFDS(フル・ディメンジョナル・サウンド),マーキュリーのマーキュリー・リビング・プレゼンス,エヴェレストの35ミリ・マグネチック・フィルム使用の3チャンネル録音,などなど。各レーベルとも個性を主張し自分のレーベルこそ1番との思いで録音をしていったものです。 また,その録音方式には大きく分けて2つの方向に分かれていました。 一つは,家に居ながらにして素晴らしいホールの最上の席に座って音楽を聴く感覚を追求したもの。 もう一つは,オーディオ・マニアを満足させる,現実の演奏では聴く事は出来ないが,作曲家,指揮者,演奏者が聴かせたい部分をマイクで拾い出し強調して聴かせる録音効果重視の方式です。ここで言う録音効果とは決して演奏や曲の本質を壊すものではなく,あるべき所にあるべき音があるように録るというものでした。そのことに成功し,クラシック音楽を愛するものからオーディオ・ファンまでを満足させたのが,イギリスのデッカであり,「ハイファイならデッカ」と呼ばれるようになったのです。 そのころの一連の録音は,録音技師がまさに「もう一人の芸術監督」でした。 当時の録音機器はダイナミック・レンジが狭く,自然な録音ではノイズに埋もれるか,高級な再生装置を持つものだけが再生しうる録音になる可能性が高いものでした。そこで,ppで演奏されながらもはっきりと聴こえるように,劇的な効果を上げる部分ではさらに鮮明な音を捕らえて強調するようにしていたのです。 デッカは一貫してその「ブルー」と言われる高原の朝の空気のように澄んだデッカ・トーンを基調に鮮烈な録音を世に送り出してきました。アナログ時代にはエルネスト・アンセルメ指揮のスイス・ロマンド管弦楽団の一連のロシア・フランスもので一世を風靡しまし,デジタル時代になってはシャルル・デュトワ指揮のモントリオール交響楽団にその再現を行ってきました。レコードアカデミー賞の録音部門に輝いたベルリオーズの幻想交響曲をはじめ,どの録音も鮮烈な優秀録音です。 今回ここで取り上げたのはそのデュトワ指揮モントリオール交響楽団が1986年6月に録音したホルストの「惑星」です。この曲のブームを作ったカラヤン指揮ウィーン・フィル(デッカ)の録音を挙げるまでもなく高級オーディオのハイファイ録音試聴ディスクに用いられる録音効果がディスクの出来を左右する曲です。 ここでの聴きものはなんと言っても「魔術の星『天王星』」です。「木星」も弦のきらびやかな立ち上がり方が録音の善し悪しを判定する材料になるためよく試聴されますが,私がこの曲のディスクを購入して真っ先に聴く部分はこの「天王星」になってしまったほどです。 その理由は絶対に演奏会では,いや,生演奏では聴くことが出来ない音が入っているからです。金管楽器がユニゾンで魔術師を予感させるテーマを吹き,ファゴットがゴソゴソと蠢き出します。シロフォンも含んだ怪しい炎のような曲調から第2主題に入り,冒頭のテーマがトロンボーンとテューバで吹かれた後第3主題に入り,それが最高潮に達して一時静まって弦楽器とハープで嵐の前の静けさ(いや,台風の時に一瞬だけ目に入って静まった後と言った方がいいでしょうか?)の後に金管楽器でまたも冒頭の主題が強奏された後に,その瞬間は訪れます。このディスクでは5分15秒でした。 ビックリしました。「こんな音がしちゃっていいの?」です。スピーカーがバタバタと振動するのが目で確認できます。そしてオーディオを聴く快感になりました。このコンビでパイプ・オルガンの入る曲ではff部分でこの瞬間が聴けるのです。パイプ・オルガンの音も特徴的で,生演奏や他のレーベルで聴くと「びや〜んん」ですが,このコンビでは「ぼーんんっ」なのです。(かといって全然違うとは思う事がないのですから立派です。) 参考までに(何のだ?!)この快感が得られる曲目と演奏時間を。 |
|
| サン・サーンス エルガー |
交響曲第3番「オルガン付き」 第2楽章後半冒頭部分(有名ですね) 創作主題による変奏曲(エニグマ変奏曲) 第14変奏(最終章) 4分48秒(なおオルガンはオプションで最近の録音では必ず演奏されていますが,実演ではなくても正しい演奏です。) |
|
| P.S. このコンビでチャイコフスキーのマンフレッド交響曲入れてくれないでしょうかね? |
||
理想の実現 
指揮:レオポルド・ストコフスキー 演奏:ニューフィルハーモニア管弦楽団 (現 ザ・フィルハーモニア) DECCA 433 687-2 |
オーケストラが録音できるようになってすでに半世紀以上が過ぎましたが,どんなに録音技術が進歩しても元になる演奏者たちが巧くなければどうにもなりません。指揮者は理想の音を出すためにオーケストラに対して自分の意志を指揮棒で伝えリハーサルを重ねてます。 そして本番。 演奏者は人間ですから指揮者の理想を本番では落としてしまったり,ミスを犯したりして結局は理想の演奏は「また次回」と相成るのです。 しかし,どうしてもうまくいかない場合はどうするのか? その答えが録音の編集でした。一気に演奏する演奏会とは違い何度でも(時間や演奏者の耐久力の制限はありますが)やり直しがきくのです。そして良いところだけを繋げてできあがりです。 この弊害は技術的には完璧でもどうしても音楽の流れが断ち切られるためにインテンポに近づいてしまうことです。結果として巧いけれど味のない演奏が残るのです。喩えて言えばいくつもの行程を分業がして流れ作業でできあがる工業製品と一人の職人が責任を持って仕上げる製品でしょうか。 SPの時代には逆に音楽は片面に入る分だけ一気に演奏し,その時間ごとの演奏として楽しめる物でした。しかし,演奏が分断されることを嫌って録音に消極的であった演奏家も多かったのです。これが正常な演奏家の心理ではないでしょうか? また,長い時間の演奏が録音できるようになり演奏が編集しなくても収録できるようになった昨今においても「音楽とは存在ではなく生起なのです。音楽は生起します。音響は音楽ではありません。音楽が音響となるのです。」と言う理念の元に死ぬまで録音を拒んできたチェリビダッケは極端であったにしても,今でも録音には消極的であるアーティストが存在するのはその編集作業によるところが大きいとも思われます。 最近になって続々と素晴らしい放送録音が正規盤として発売されているクーベリックなどは実演とレコーディングでこれほどまでに違うかと驚かされると同時に,レコーディングによるレコードの限界をも感じさせてくれます。 この弊害と言える部分を逆手に取った指揮者も存在しました。 カラヤンは実演を聴きに来てくれた人に,帰りにはその実演と同じ曲目のレコードを持ち帰らせるということさえ行いました。もちろん演奏は傷のない完璧な物。実演の興奮は少ないものの,十分堪能できる物です。 前置きが長くなってしまいました(いつも(^^;; )。今回ご登場いただくのは,「音の魔術師」ことストコフスキーです。この「迷演集」をご覧になった方はストコフスキー,シェルヘン,ケーゲル,クナッパーツブッシュ,ゴロワノフと言った一般に「怪演」と言われる物を残した人々が出ていないのはおかしいとお思いだったでしょう。前記の人々は容易に想像がつくし,ここを見ていただいている方々にとっては,「今更ここに書くまでもないかな?」と思ったからですが・・・。 このCDを聴いた方はいるでしょうか? チャイコフスキーの交響曲第5番です。演奏はニュー・フィルハーモニア管弦楽団,録音は「ハイファイと言えばデッカ」の英デッカ。みなさんご存じの有名名曲です(今ドコモのカラーimodeのコマーシャルに2楽章が使用されていますね。)。 ストコフスキーは,原曲がより効果(良く言えば「華麗さ」悪く言えば「ド派手な」)を発揮するようにスコアに手を加えるのはもちろんのこと,オーケストラの録音にまでアレンジの手を伸ばしてしまいました。オーケストラ演奏録音の限界に気づくと同時に,録音の可能性に注目し,その可能性に賭けたのです。そしてこんな演奏が生まれました。 チャイコフスキーの交響曲第5番を聴いてみましょう(これも第1話でご紹介した録音のように再発売盤ではなぜか灰汁が消えてつまらないリマスターのせいで驚きが伝えられないのが残念です。指揮者の意志を尊重して欲しい物です)。 第1楽章です。冒頭からマルチマイク炸裂!!フルート出過ぎ(笑)ホルンの生音が(笑)そして6分20秒付近と13分20秒付近です。この録音の白眉(苦笑)弦楽器が美しく歌い上げるフレーズで,ある瞬間に明らかに録音レベルが上下します。彼は弦楽器にこのようなクレッシェンド&デクレッシェンドを求めたが叶わず,この方式にしか彼の理想を実現すべき手段はなかったのでしょう。 第2楽章でも同様のことが続きます。 「をい そのバストロいいね〜(ニヤっ)」 「をいをい(^^;; そのピチカートはそんなにデカイ音なんか(笑)」 第4楽章では, 「今カットしなかったか?」 等々・・・。最後のトランペットとホルンで高々と吹き上げるメロディーでスラーがかかっていますが,楽譜でそうなっていると他の演奏を聴くまで信じていました。 迷演と言うことでここに載せてはいますが,演奏は素晴らしく,名演でもあります。話題になったゲルギエフ指揮のウィーン・フィルのライブにも勝とも劣らない演奏,と個人的にはは思っています。 ちなみに,幸か不幸かこれが私の録音チャイ5初体験であり,強烈な印象を残すと同時にストコフスキーに注目(耳)するきっかけともなりました。 ストコフスキーは自分勝手にやりたいように原曲をいじってみたり,録音の聴卓に座って音をいじるのが好きだったのでしょうか? そうではありません。彼は自分の理想を実現したかっただけなのです。 曲から受ける印象とそれを聴衆に一番的確に且つ効果的に聴かせるにはどうすればいいのか?その答えが効果的に聴かせるための編曲や一部の改変であり,レコーディングにおけるマルチマイクによる楽器のピックアップだったのです。通常の演奏では埋もれるパートであっても彼の脳裏に響く理想の曲の形はこの録音なのです。そう思ってもう一度聞き直してみてください。 美しくつながるフレージングの見事さ,変幻自在でありながら破錠しないテンポ,わくわくさせる音楽の盛り上げ方,この曲にはこんなメロディーが隠されていたのか?といった瞬間,等々。驚きと発見で音楽の楽しさいっぱいの録音です。 ゲテモノ的な捉え方だけではなく彼が一流の音楽人であった証としてもう一度聞き直してみて欲しいと思います。 ストコフスキーが偉大な指揮者であったことが実感できることでしょう。 なお,現在入手できる盤では各楽器のピックアップがおとなしくなり,録音レベルの極端な高低も無くされてしまっています。いつも思うことですが,再発売されるときには発売時の指揮者の意図と違ったリマスターがされてしまうことがあります。 確かにストコフスキーのように誰が聴いても変に聴こえる調整は変更したくなる気持ちも理解できますが,彼は発売された調整が自分の理想であるからこそ発売を許可したのであることを考えると再発時のリマスターには一考の余地があるといえるでしょう。 |
|